




日野市役所ではどんな人たちがどのように働いているのか。
そこで、職種の異なる職員の方々に集まってもらい、大いに語り合ってもらいました。
入所のきっかけ、入所後に感じたギャップ、働く環境など本音トークをご紹介します。
-
環境共生部
下水道課2001年入所
Aさん
-
教育委員会教育部
庶務課2003年入所
Bさん
-
健康福祉部
セーフティネット
コールセンター2018年入所
Cさん
-
企画部
企画経営課2010年入所
Dさん
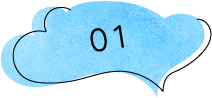
まずは日野市役所を選んだ理由を教えてください。

Bさん
大学卒業後、建築設計事務所でアルバイトをしていたのですが、母から「市役所の広報に建築職の職員採用募集が出ているから受けてみたら」と勧められたのが入所のきっかけです。建物をつくる仕事に就きたかった私には、母親になりたいという夢もあったので、仕事と子育ての両立ができそうな日野市役所を選びました。

Aさん
自分の場合、自宅から近かったからかな(笑)。高校生の時にニュージーランドでホームステイを経験した際、週末には家族や近くに住む親戚が集まって一緒に過ごしているのを見ていいなぁと思って。家族を大事にする生き方に心の豊かさを感じたんです。市役所だったら、自分もそういう生き方ができるのではないかと思い入所を決めました。

Cさん
私はお二人とは違って中途採用。最初は民間企業に勤めて、その後、図書館司書になり、図書館情報学の講師の仕事をしていました。日野市役所の民間企業等経験者枠の採用募集に応募したのは、社会課題に直接アプローチできそうだったから。出産を機に、子どもの貧困など子どもを取り巻く環境にすごく関心をもつようになったんです。

Dさん
自分はやりたいことが何なのか全然わからなくて…。就活中、いろんな業種の説明会に参加しましたが、どれもピンとこない。たまたま地方公務員の仕事を調べてみたら、多岐にわたっていて、それぞれ専門性があることがわかりました。ここでなら、働きながら自分のやりたいことが見つけられるかもしれないと考え、採用試験を受けました。
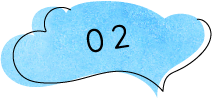
実際に入所してみて、入所前のイメージとのギャップはありましたか。

Aさん
Dさんが言ったように、市役所の仕事は多岐にわたっていることに驚きました。学校や保育園、児童館の運営から学校給食の提供、ごみ処理まで。さらに日野市の場合、病院も経営しています。民間企業なら別々の会社で運営する事業を一つの組織で行っている。入所して20年以上経ちますが、いまだに驚きを感じています。

Dさん
入所前はいわゆる“お役所仕事”のイメージをもっていたのですが、入ってみると、そうしたイメージから脱却したいと思っている人が多いことに気づきました。意外でしたね。

Cさん
私も入所前は“お役所仕事”だから、毎日定時で上がれるものだと思っていました(笑)。ところが、「こうしたい、ああしたい」って深掘りしていけばいくほど、仕事って面白くなるんです。それをやっていると定時では上がれない(笑)。

Bさん
同感です。実を言うと、市役所の仕事は地味でやりがいも少なく、面白みがないと決めつけていたんです。ところが入ってみたら、「小さなことでも、自分の仕事が誰かの役に立つことがある」と実感できる機会があって。以来、仕事がものすごく面白くなりました。ただ、仕事を掘り下げるほど楽しい反面、時間もかかってしまう。

Cさん
思うに、時間がかかる理由として、組織の縦割りも影響しているように感じます。一方で、組織の枠を超えて横断的に取り組もうと考えている人もいる。市役所には保守的な人ばかりと思い込んでいましたが、発想が柔軟で行動的な人もいることがわかり、うれしい誤算でした。
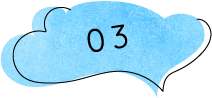
職場の雰囲気や人材育成についてどう感じていますか。

Bさん
自分のライフステージに合わせて仕事ができる環境だと思いますね。休暇制度が整い、その利用を後押ししてくれる職場の理解がある。私の場合、二人の子どもを出産した時は仕事よりも子育てを優先し、子どもが小学生になった今は仕事のほうにシフト。こんなに自分のやりたいようにやらせてもらえるなんて、入所するまで知りませんでした(笑)。

Dさん
自分も4カ月間ほど育児休暇を取りました。事前に上司に相談し、仕事の調整を図りましたが、休みやすい環境をつくってもらえたのはありがたかった。そうした雰囲気づくりは役所ならではの良さだと思いますね。

Aさん
職場の雰囲気は家族的で和気あいあいとしているよね。詳しくは『絶対に人には見せてはいけない日野市の職員手帳※』を読んでください(笑)。Dさんたちがつくったんだよね。 ※日野市の職員手帳は、日野市の図書館に置いてあります。

Dさん
はい、広報担当だった時に。2019年に発行したのですが、日野市の魅力や市職員の仕事内容などがユーモアたっぷりに本音で語られています。

Aさん
面白いですよね、自虐ネタもあって(笑)。

Dさん
そもそも発行のねらいは職員のマインドを上げるためで…。「役所のイメージを変えたい」「新しいことをやりたい」と思いながら、なかなか一歩を踏み出せていないのが課題だったので、まずは職員がワクワクしながら、それぞれの仕事を自分事としてとらえることを目指そうと試行錯誤する中で生まれたのが、この手帳なんです。

Cさん
確かに、他人事ではなく自分事にすることで、仕事に取り組む姿勢は変わってきますよね。いかに自主的に動ける人を育てて、“自走する組織”にしていくか。これは私にとって大きなテーマ。だからこそ、若い人たちにはまずは自分で考え、動いてもらう。多少ミスをしてもいいので、その人の成長を見守る。それが私の人材育成のスタンスですね。

Bさん
人材育成については私は試行錯誤中。今の若い世代はマニュアルが欲しいけれど、自分たちはマニュアルがない中、現場で育てられてきた世代なので、そのギャップをどう埋めるか。これはもう話すしかないですね。お互いがわかりあえるようにコミュニケーションをとっていくことが一番大事かなと思っています。

Dさん
正直言って、役所の仕事をすべてマニュアル化することは難しい。でも、“木”で例えるなら、太い幹の部分はマニュアル化できるし、したほうがいい。それが働きやすい職場づくりにつながりますから。ベテランも若手も歩み寄って話し合いながらマニュアル化を進めていくことは、これからのデジタル化において欠かせない作業だと思います。
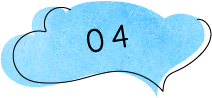
ズバリ! 日野市役所で働く魅力はどんなところにありますか。

Bさん
自由なところですね。自治体の仕事って、どんなに思いがあってもルールに従うことが大前提。でも日野市の場合、もちろんルールはあるけれど、それを超えてチャレンジさせてくれる風土があります。今、私たちが進めている学校のプール改革がまさにそう。老朽化した屋外プールで天候に左右されながら授業するというこれまでの学校プールの代わりに、民間の屋内プールを活用して年間計画で水泳専門コーチの指導を取り入れようというものです。

Cさん
そういう動きは全国的に広がっていますよね。

Bさん
そうなんです。だから、コロナ禍で学校も臨時休校になり、大きな変化があったタイミングでプール改革を提案したところ、市内4校で実現、現在では6校に拡大しました。しかも、「やってよかった!」と評価の声もいただけました。公共施設マネジメントの観点から、学校でプールの授業を行うのが当たり前という価値観を変えられたことは、未来に続く大きな一歩でした。

Aさん
そういう地に足の付いた取り組みができるのが日野市役所の魅力。以前、都庁に2年間出向した経験があるのですが、確かに私たちは東京都の職員と比べると、一つの分野を極めてはいないかもしれない。でも、社会全体を俯瞰して見て幅広い知識があり、職員同士の連携プレイもスムーズにできる。それが私たちの強みだと思います。

Cさん
本当にそうですね。日野には、地域をより良くしたいと思う市民の方が多く、そうした人たちと一緒に仕事ができることに私は魅力を感じています。市民、役所、企業、それぞれの特長を掛け合わせて、ハブになって課題解決のために取り組んでいけるダイナミックさ。民間企業では得られない仕事の面白さがここにはあると思います。

Dさん
皆さんが言われたように、地域課題の第一線で働けることが日野市役所で働く醍醐味でしょう。それに加えて、職住近接といったプライベートの充実も図れる。なによりチャレンジを応援する風土があり、若い力に期待する仲間がいます。ぜひ一緒に日野市役所を盛り上げていきましょう。

